
|
についてほとんど知識がありませんでした。そこで、観察会で見られる野鳥を、カードや写真を使って事前指導の時間に紹介し、観察するときの注意をしたことが、観察中の意欲的な態度となって現れました。
また、ビンゴカードは、開放的になりがちな校外学習で、観察意欲を継続させ、楽しみながらも多くの発見を持たせることに有効でした。
子ども遠の感想から、豊かな自然の姿にふれあった喜びと、それを大切にしたいという思いが伝わってきます。何も無いような冬の公園で、ドングリを拾ったり、木の根もとをそっと覗いたり、子ども連の興味は尽きることがありませんでした。多くの子どもが、また行きたい、友達や家族に知らせたいと述べていました。身近にありながら、見過ごしていた豊かな自然に対し、深い感動と驚きを持つことができました。そして、その後も何度か、子ども達から観察の報告を受けることができました。
今、子供たちに必要なのは、自然とのふれあいです。都市化の進む中、大人を含めて、自然との関わりが薄れてしまいました。そして、自然を見る目、自然を感じる心が失われてきています。自然観察ビンゴも、その対象となる自然がなければ実行することができません。郊外の自然が残されている学区では実施可能でも、町中ではできないとお考えの方も多いと思います。
ところが、自然はとてもたくましいもので、場所さえあればそこに復元されてきます。
プールで成長するヤゴがよい例です。ヤゴは、単独では生活できません。水泳指導のシーズンが終わったときから、微生物の繁殖が始まり、冬を迎え、5月には、ヤゴを始め、ミズカマキリなどの水生昆虫が住める環境ができあがっているのです。
草取りをしない場所を、校庭の一部に確保してください。できれば近くに、樹木があるとさらにいいです。もちろん、池などの水場があれば最高です。始めは雑草です、それも、乾燥に強い、イネ科の困り者です。でもそこから生態系が始まります。植物があることにより、気温の上昇や、乾燥を和らげ、次々と他の生き物を呼び込んできます。バッタやイトトンボなどを発見できるようになるのは、それほど時間がかかりません。
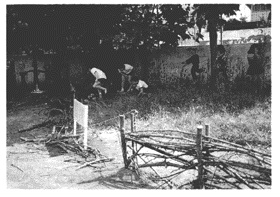
ビオトープ2)の写真
囲には、校庭の樹木を剪定したときに出た枝を、適当な長さに切って組み合わせました。
フィールドビンゴの他にも、このような自然観察を参加者が、意欲的に取り組めるような手法として、「ミクロハイク」「色を探そう」「同じものを探そう」3)などがあります。項目と内容を工夫して、様々な自然観察の場面で活用していただきたいと思います。
そして、自然と触れ合う喜びを子供たちと共に体験してほしいと思います。
文献
1)J・B・コーネル:ネイチャーゲーム?T、?U、柏書房(1986)
2)千葉県環境部:環境学習ガイドブック、千葉県環境財団(1994)
3)日本生態系協会:学校ビオトープマニュアル(1995)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|